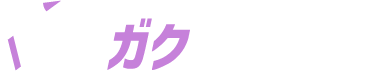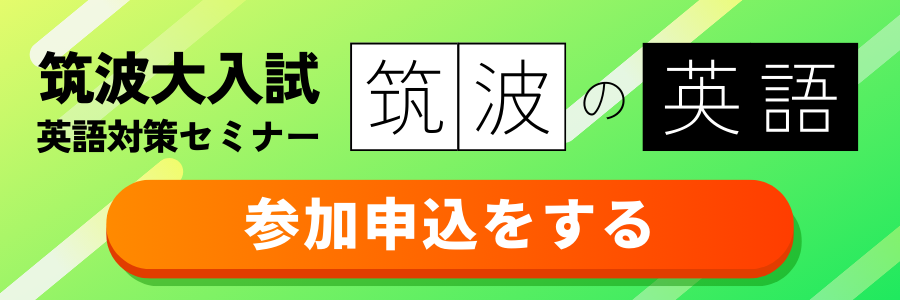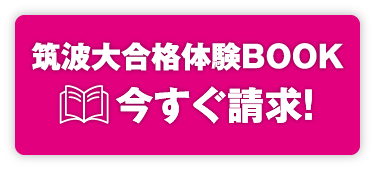今回は、筑波大学の「総合選抜」について、特に理系Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いや入試のポイントを詳しく解説します。
受験生のみなさん、こんな悩みや疑問をお持ちではありませんか?
・「総合選抜って何?従来の入試とどう違うの?」
・「理系Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いがよく分からない…」
・「どの区分で受験すれば希望の学類に入れるの?」
・「入学後の移行制度って実際どうなの?」
そんな疑問を解決するために、筑波大学の入試を知り尽くした私たちが、総合選抜の仕組みから入試対策まで、受験生目線でお答えします。
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
\PR/筑波大学の最新入試傾向から筑波大英語対策授業まで全て無料で参加できます!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!
目次
総合選抜って何?まずは基本を押さえよう

従来の入試制度との違い
従来の入試制度では、高校時点で「工学システム学類」「情報科学類」など、具体的な学類を決めて受験し、入学後はその学類で4年間学習しなければなりませんでした。しかし、筑波大学は2021年度から「総合選抜」という新しい入試制度をスタートしました。これまでの「○○学類」を直接受験する制度とは大きく異なります。
総合選抜制度
総合選抜制度では、「文系」「理系Ⅰ」「理系Ⅱ」「理系Ⅲ」の4区分で受験し、入学後は「総合学域群」に所属して、1年間で幅広い学問を学習します。そして、2年次に本格的な専門学類を選択(これを「移行」と呼びます)することになります。
なぜ総合選抜制度が生まれたの?

現役筑波大生の声を聞くと、「高校時点では将来やりたいことが明確でなかった」「大学で学んでみて本当に興味のある分野が見つかった」という学生が多いんです。
総合選抜は、そんな学生のニーズに応えるために作られた制度です。入学後に幅広い学問を俯瞰し、自分の適性や興味を発見してから専門を決められるのが最大の魅力です。
理系Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基本データを比較

まずは、3つの区分の基本的な違いを見てみましょう。
| 区分 | 募集人員 | 主な想定分野 | 優先移行先の例 |
| 理系Ⅰ | 145名 | 物理・化学・数学中心の理工学分野 | 数学類、物理学類、化学類、工学システム学類 |
| 理系Ⅱ | 49名 | 生物学中心の生命科学・環境科学分野 | 生物学類、生物資源学類、医療科学類 |
| 理系Ⅲ | 84名 | 情報科学・データサイエンス分野 | 情報科学類、情報メディア創成学類 |
ポイント!
・理系Ⅰが最も募集人員が多く、幅広い理系分野をカバー
・理系Ⅱは生物系に特化した区分・理系Ⅲは情報系に特化した区分
・理系Ⅲは情報系に特化した区分
移行制度の仕組み

移行って実際どうやって決まるの?
移行先は以下の要素で決まります:
- 学生の志望順位:希望する学類・専門学群を順位付け
- 学類の受入順位:1年次の成績や適性を基に学類が順位付け
- 優先枠の存在:特定の選抜区分に設けられた優先枠
優先枠って何?
これが総合選抜の最重要ポイントです。各学類では、特定の選抜区分で入学した学生を優先して受け入れる枠があります。
例:数学類(受入定員10名)
・理系Ⅰ優先:8名
・理系Ⅲ優先:1名
・区分問わず:1名
つまり、数学類を目指すなら理系Ⅰで受験するのが圧倒的に有利なんです。
現役筑波大生が教える移行のリアル
実際に総合選抜で入学した先輩たちに聞くと:
・優先枠があるからといって安心はできない。1年次の成績が重要
・予想していた分野と違う分野に興味を持った
・1年次で色々な分野を学べるのは本当に良かった
という声が多いです。優先枠は確かに重要ですが、入学後の努力も欠かせません。
理系Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの詳細分析

学群別主な優先移行先一覧
| 学類名 | 理系Ⅰ優先人数 | 理系Ⅱ優先人数 | 理系Ⅲ優先人数 |
| 数学類 | 8名 | – | 1名 |
| 物理学類 | 10名 | – | – |
| 化学類 | 10名 | – | – |
| 応用理工学類 | 27名 | – | – |
| 工学システム学類 | 30名 | – | – |
| 社会工学類 | 15名 | – | – |
| 生物学類 | – | 5名 | – |
| 生物資源学類 | – | 5名 | – |
| 地球学類 | 6名 | 2名 | – |
| 医療科学類 | – | 4名 | – |
| 情報科学類 | – | – | 16名 |
| 情報メディア創成学類 | – | – | 12名 |
| 知識情報・図書館学類 | – | – | 25名 |
| 数学類 | 8名 | – | 1名 |
理系Ⅰ:王道の理工学コース
こんな人におすすめ
・物理・化学・数学が得意
・工学系に興味がある
・幅広い理系分野から選択したい
入試対策のポイント
・数学:微積分、ベクトル、確率統計を重点的に
・物理:力学、電磁気学の基礎を固める
・化学:理論化学、有機化学をバランスよく
理系Ⅱ:生命科学のスペシャリストコース
こんな人におすすめ
・生物学が得意・好き
・医療・環境分野に興味がある
・実験や観察が好き
主な優先移行先入試対策のポイント
・生物:分子生物学、遺伝学を重点的に
・化学:生物化学の基礎となる有機化学を強化
・数学:統計学の基礎を押さえる
理系Ⅲ:未来のIT人材育成コース
こんな人におすすめ
・情報・プログラミングに興味がある
・論理的思考が得意
・データサイエンスに関心がある
入試対策のポイント
・数学:離散数学、確率統計を重視
・情報:アルゴリズムの基礎理解
・論理的思考力を鍛える問題演習
入試科目と配点 – 具体的な対策法
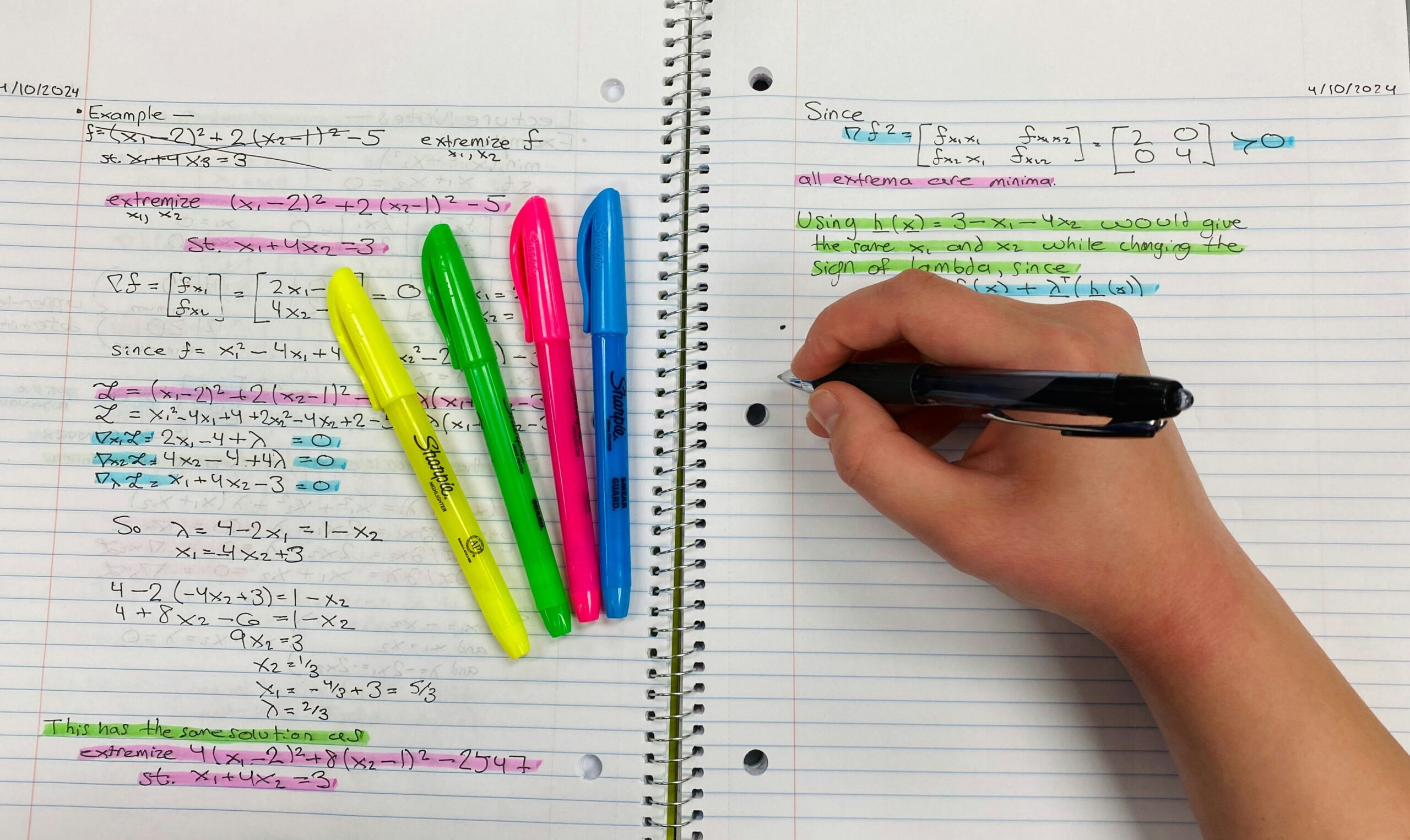
共通テスト対策(全区分共通)
| 教科 | 科目数 | 配点 | 備考 |
| 国語 | 1 | 200点 | |
| 数学 | 2 | 200点 | 数学ⅠA・ⅡB など |
| 英語(外語) | 2 | 200点 | リーディング+リスニング 各100点換算 |
| 地歴・公民 | 1 | 100点 | 1科目選択(例:現代社会など) |
| 理科 | 2 | 200点 | 基礎2科目 or 発展1科目×2 |
| 情報 | 1 | 50点 | 情報Ⅰ |
| 合計 | 8 | 950点 | 教科数6 |
個別試験(2次試験)対策
【理系Ⅰ・理系Ⅱ(共通)】
| 教科 | 配点 | 対策ポイント |
| 数学 | 500点 | 数Ⅲ・Cまで含む発展的内容に対応 |
| 英語 | 500点 | 英文読解・英作文・リスニング対策 |
| 理科 | 500点 | 2科目選択(例:物理+化学/生物+地学) |
| 合計 | 1500点 | バランス重視の出題 |
【理系Ⅲ(数学重視)】
| 教科 | 配点 | 対策ポイント |
| 数学 | 600点 | 高度な論述力・情報処理的思考力が問われる |
| 英語 | 500点 | 長文読解・論理展開に強くなる必要あり |
| 理科 | 400点 | 2科目選択(理系ⅠⅡより比重が軽い) |
| 合計 | 1500点 | 数学重視型の配点 |
区分別の特徴と対策方針
| 区分 | 特徴 | 対策ポイント |
| 理系Ⅰ | 物理・化学・数学のバランス型 | 3教科満遍なく力をつけること |
| 理系Ⅱ | 生物の比重が高い | 生物を軸にしつつ他教科も確実に点を取る |
| 理系Ⅲ | 数学・情報的思考力を重視 | 数学で高得点を取れるよう思考力・記述力を強化する |
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
\PR/筑波大学の最新入試傾向から筑波大英語対策授業まで全て無料で参加できます!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!
受験戦略 – どの区分を選ぶべきか
戦略1:将来の目標から逆算する
工学系志望の場合 → 理系Ⅰ一択
理系Ⅰは工学系学群への優先枠が圧倒的に多く、機械工学、電気電子工学、土木工学などの伝統的な工学分野を目指すなら最適解です。
具体的な進路例
・社会工学類:都市計画、経営工学
・応用理工学類:材料工学、応用物理
・工学システム学類:機械工学、電気工学
選択のメリット
・募集人員が最も多い(約200名)
・進路選択の幅が広い
・企業からの評価が高い分野
生物・医療系志望の場合 → 理系Ⅱが有利だが、理系Ⅰからでも移行可能
生命科学、医学、農学系を目指すなら理系Ⅱが直接的ですが、理系Ⅰからでも十分に進路変更は可能です。
理系Ⅱの優位性
・生物学群への優先枠
・医学群への特別枠
・生命環境学群への直接進学
理系Ⅰからの移行戦略
・1年次に生物学を履修
・研究室訪問で興味を具体化
・学群移行試験で実力を証明
情報系志望の場合 → 理系Ⅲが最適、でも数学類なら理系Ⅰも検討
情報科学、データサイエンス、AI分野を目指すなら理系Ⅲが新設された背景もあり最適です。
理系Ⅲの特徴
・情報学群への特別枠
・最新の情報技術にフォーカス
・産業界からの注目度が高い
数学系なら理系Ⅰも有効
・数学類への進学が可能
・理論的基盤を重視
・研究職への道筋が明確
戦略2:得意科目から考える – 自分の強みを活かす
物理・化学が得意 → 理系Ⅰで勝負
物理と化学を得意とする受験生にとって、理系Ⅰは最も力を発揮できる舞台です。
入試での有利点
・二次試験で物理・化学を選択可能
・得意科目で高得点を狙える
・競争相手も同じ土俵で勝負
学習戦略
・物理は力学・電磁気学を重点的に
・化学は理論化学・有機化学をバランス良く
・数学との連携を意識した学習
生物が得意 → 理系Ⅱで専門性をアピール
生物学に強い関心と実力を持つ受験生は、理系Ⅱで専門性を前面に出すことが効果的です。
生物選択の戦略
・分子生物学の基礎を固める
・実験考察問題に慣れる
・最新の生物学トピックスにアンテナを張る
差別化のポイント
・生物オリンピック等の実績
・研究発表の経験
・環境問題への関心
数学・論理的思考が得意 → 理系Ⅲで差をつける
数学や論理的思考力に自信がある受験生は、理系Ⅲで大きなアドバンテージを得られます。
数学力の活用法
・アルゴリズム思考の習得
・プログラミング能力の向上
・数学的モデリングの理解
戦略3:競争率を考慮する – データに基づく冷静な判断
現役筑波大生の分析データ
⭐️理系Ⅰ:募集人員が多いが競争も激しい
・募集人員:約200名(最多)
・競争倍率:3.5〜4.0倍
・合格者の特徴:バランス型、高い基礎学力
戦略のポイント
・標準的な問題で確実に得点
・苦手科目を作らない
・模試での偏差値60以上を維持
⭐️理系Ⅱ:募集人員が少ないが専門性が高い
・募集人員:約80名
・競争倍率:2.5〜3.0倍
・合格者の特徴:生物への強い関心、専門性
戦略のポイント
・生物で他の受験生と差をつける
・研究への関心を明確に示す
・面接や小論文で専門性をアピール
⭐️理系Ⅲ:新しい分野で将来性抜群
・募集人員:約60名
・競争倍率:2.0〜2.5倍(まだ穴場)
・合格者の特徴:情報技術への関心、論理的思考力
戦略のポイント
・数学と情報の両方に強みを持つ
・プログラミング経験があると有利
・最新技術への関心を示す
入学後のサポート体制

移行支援プログラム
筑波大学では、移行先選択のために充実したサポートを提供しています。まず、全学必修科目である「学問への誘い」では、様々な分野の教員がオムニバス形式で講義を行い、学生が幅広い学問分野を俯瞰できるように設計されています。この科目を通して、自分がまだ知らない分野の魅力を発見したり、逆に想像していた分野とのギャップを感じたりすることで、より適切な進路選択ができるようになります。
また、「履修・移行ガイドブック」では、各学類の詳細な情報や移行のためのロードマップ、そして何より参考になる先輩の体験談が掲載されており、移行先選択の貴重な判断材料となります。現役筑波大生によると、「先輩の体験談が一番参考になった」という声も多く聞かれます。
さらに、夏休み期間中には「模擬判定」が実施され、現時点での成績をもとに移行先を予測してもらえます。これにより、志望変更が必要かどうかの判断材料が得られ、後期の履修計画や勉強方針の調整に活かすことができます。
アカデミックサポートセンター
個別相談にも対応してくれるアカデミックサポートセンターは、現役筑波大生が語る「本当に心強い存在」です。移行に関する不安や疑問を気軽に相談できる環境が整っており、一人ひとりの状況に応じたアドバイスを受けることができます。
よくある質問

Q1:理系Ⅰで入学したけど、情報系に移行できる?
A1:もちろん可能!ただし優先枠がないので、しっかりとした成績と志望理由が必要です。
Q2:移行に失敗したらどうなる?
A2:基本的に全員どこかの学類に移行できます。第一志望に行けなくても、筑波大学の学問レベルは高いので心配無用!
Q3:1年次はどんな勉強をするの?
A3:幅広い基礎科目を学びます。専門科目は2年次からなので、じっくり将来を考えられます。
まとめ:総合選抜で筑波大学合格を目指そう!

筑波大学の総合選抜は、従来の入試制度とは全く異なる新しいシステムです。重要なポイントをまとめると以下の通りです。
選択のポイント
- 将来の目標に合わせて区分を選択
- 得意科目を活かせる区分を選択
- 優先枠を意識した戦略的選択
入試対策のポイント
- 共通テストの基礎固めが重要
- 区分別の特徴を理解した対策
- 情報Ⅰなど新科目への早期対応
入学後のポイント
- 1年次の成績が移行に直結
- 幅広い学問を学んで視野を広げる
- サポート体制を積極的に活用
総合選抜は、「まだ将来が明確でない」「幅広く学んでから決めたい」という受験生には絶好の制度です。一方で、明確な目標がある場合は、戦略的に区分を選択することで有利に進められます。
筑波大学受験を検討されている皆さん、総合選抜について詳しく知りたい方は、ぜひツクガクの無料相談をご利用ください!現役筑波大生が皆さんの疑問にお答えします。
筑波大学合格への第一歩は、正しい情報収集から

ツクガクでは、筑波大学の入試を知り尽くした現役筑波大生講師が、一人ひとりの状況に合わせた個別指導を行っています。総合選抜の攻略法から学類別の対策まで、筑波大学合格のためのサポートを全力で行います!
まずは無料相談で、あなたの筑波大学合格への道筋を一緒に考えましょう!
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
ツクガク公式LINE
\PR/筑波大学の最新入試傾向から筑波大英語対策授業まで全て無料で参加できます!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!